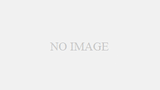夢のマイホームや理想の投資物件を購入した後に、「聞いていなかった」「契約内容が違う」と後悔する人は少なくありません。不動産の契約は専門用語が多く、複雑な条項が多いため、十分に確認しないままサインしてしまうケースもあります。購入後のトラブルを防ぐには、契約前にどんな内容をどうチェックすべきかを理解しておくことが不可欠です。ここでは、安全に取引を進めるための契約内容チェック方法を解説します。
1. 契約書の「基本情報」を確認する
まず最初に確認すべきは、契約書の基本項目です。些細な誤記でもトラブルの原因になることがあります。
- 売主・買主の氏名・住所・印鑑が正確に記載されているか
- 物件の所在地・地番・構造・面積などが登記簿謄本と一致しているか
- 付帯設備(エアコン・照明・給湯器など)の有無が明記されているか
特に中古物件の場合、付帯設備の状態確認が曖昧だと「壊れていた」「使えなかった」といったトラブルにつながります。必ず現物を確認し、契約書に明文化しましょう。
2. 支払い条件とスケジュールの明確化
契約時には、支払いのタイミングと金額をしっかり把握する必要があります。
- 手付金・中間金・残金の支払い時期と金額
- 住宅ローン特約(ローンが不成立の場合の契約解除条件)
- 支払い遅延時のペナルティや違約金の有無
特にローン特約は買主を守る重要な条項です。書面上に「金融機関の審査が通らなかった場合は白紙解除可能」と明記されているか確認してください。
3. 引き渡し条件と違約条項を確認する
契約書には「いつ・どの状態で物件を引き渡すか」が定められています。ここが曖昧だとトラブルの温床になります。
- 引き渡し日が具体的に設定されているか
- 現状有姿(げんじょうゆうし)での引き渡しか、修繕を条件にしているか
- 引き渡し遅延時の違約金の有無と金額
「現状有姿」とは、現状のまま引き渡すという意味です。この場合、売主に修繕義務がないため、購入後に不具合が見つかっても自己負担になる可能性があります。引き渡し条件は慎重に確認しましょう。
4. 瑕疵(かし)担保責任・契約不適合責任の範囲
契約後に「雨漏り」「シロアリ被害」などの隠れた欠陥が見つかった場合、売主が責任を負うかどうかは契約書の内容に左右されます。2020年の民法改正により、「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」として明文化されました。
- 売主が個人か業者かによって責任範囲が異なる
- 補修・代替・損害賠償のいずれで対応するか
- 責任を追及できる期間(通常は引き渡しから1〜2年)
「免責」となっている場合は、買主が修理費用をすべて負担することになります。中古物件では特に重要な確認ポイントです。
5. 重要事項説明書との整合性を確認する
契約前に宅地建物取引士から交付される「重要事項説明書」と契約書の内容が一致しているかをチェックしましょう。両者に矛盾がある場合、後に「説明不足」「契約違反」となることがあります。
- 建築制限・用途地域・都市計画などの法的制限が説明されているか
- 上下水道・ガス・電気などのライフライン情報が一致しているか
- 管理費・修繕積立金(マンションの場合)の記載が明確か
書類を受け取ったら、その場でサインせず、持ち帰ってじっくり読み込みましょう。分からない箇所は宅建士や第三者専門家に質問することが大切です。
6. 契約書のコピーを保管する
契約完了後は、必ず契約書と重要事項説明書のコピーを自分で保管しておきましょう。万一トラブルが発生した際、これらの書類が法的な証拠になります。電子契約の場合も、データを安全な場所にバックアップしておくことが重要です。
7. まとめ
不動産契約は複雑で、専門用語に惑わされがちですが、ポイントを押さえればリスクを大幅に減らせます。「内容を理解していないままサインしない」「口約束を信用しない」「すべて書面で確認する」——この3つを守るだけでも、トラブルの多くは防げます。購入後に安心して暮らすためにも、契約段階でのチェックを怠らないことが最も重要です。